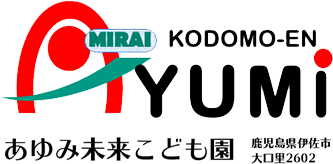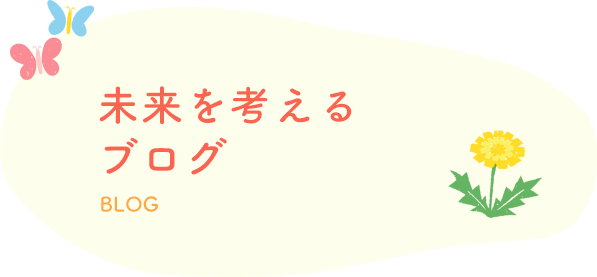幼児教育・保育の今後
自己肯定感の高い子へ
今の子供たちは自分で考え自分で行動することができない子、すなわち主体性のない子が多いといわれています。
このような子供は、「今自分は何をすべき時なのか」がわかりません。
その典型的な例が小1プロブレムに見られる子供の行動です。また日米中韓の子供(17歳以下)を対象としたアンケート調でも「自分に自信がない」と答えた子供は、日本が7割を超え、ついて韓国5割台、中米告(5割以下)という結果でした。
一方幼児期に主体性を重視した教育・保育を行うことで、自尊心(自己肯定感)が育まれます。
自尊心の高い子供は、次のような行動をとることができます。
★ 失敗よりも成功をイメージした前向きなチャレンジ
★ 壁にぶつかってもそれにたち向かう
★ 自分自身を大切に思うと同時に他人からも愛されていると思える
★ 他人と積極的に関わり、良好な関係を築ける
⼦ども主体の保育へ
これまで⽇本の幼児教育・保育は、時代の変化に伴って⼦供を取り巻く環境が変わってもほとんどその⼿法を変えずに来たと思います。
その⼿法とは保育園で⾔えば、保育⼠主導の集団保育型と⾔っていいもので、管理的であり、先⽣の⾔うことをよく聞き、⾏儀の良い、かしこい⼦を育てることが良い保育でした。
しかしながらここで育つ⼈間は、往々にして受動的な性格を持つため、保育士主導では自己肯定感は育ちにくいものです。
これからの乳幼児に必要な教育・保育は子供が主体とる教育・保育です。
|
子供主体の教育・保育 |
|
保育者主導から子供が主体的・自主的に行動し、考える保育 |