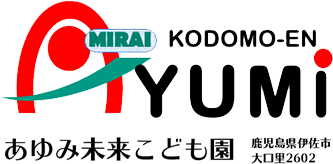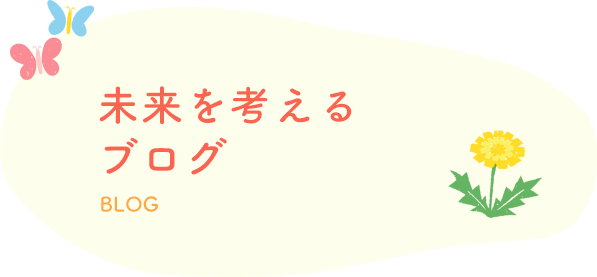日本の子育て事情
戦後日本の子育て事情について、昭和レトロ時代と呼ばれた昭和30年代とその後の年代を比較するとわかり易いと思います。
戦後の日本は昭和30年代に入ると、戦後に終わりを告げ、高度経済成長期に入りました。
私はまさにこの時代の生まれで、世の中がどんどん新しいもの変わっていくのを見てきました。我が家にきた新三種の神器(冷蔵庫・洗濯機・白黒テレビ)の中でやはりテレビが来た日は記憶にあります。
昭和30年代は、世の中が新しいものに変わっても、家族間や地域間の関係はまだ昔を残していました。夜はちゃぶ台を囲み、ご飯をたべながらの家族間の団らんがそこにはありました。その中に必ずおじいちゃんやおばちゃんがいたのです。
地域との関係もまだ機能しており、助け合いの精神が残っていました。子供たちは一人で遊ぶことは少なく、徒党を組んで、時には年齢差を超えて、遊んでいました。
昭和30年代は、昭和レトロとして昭和を知らない核家族時代・少子化時代に生まれた現代の若者にも[懐かしい、郷愁を感じる時代]として人気があるようです。
このことは、人間は戦争のない、明るい未来を予感させる社会を望むことは当然としてもすべての人間は「人間同士相互の関わりがある社会」の中にいることを望んでいるのではないかと思います。
映画ALWAYS三丁目の夕日 に出てくる下町の人間関係とかテレビ アニメのサザエさんのような家庭をだれしもが望んでいるのではないのでしょうか。
経済成長と共に地方の若者は仕事を求めて田舎を離れるようになりました。
中には中卒・高卒の子供たちが「金の卵」として集団就職することもありました。
都会に出た若者は、やがてそこで結婚し家族を持つようになると、核家族化が始まりました。
しかし世の中は変わり、家族を支えるはずのお父さんは、経済大国となった日本経済をささえる企業戦士として長時間労働を強いられ、家庭や育児は殆どお母さんに其の責任を負わせました。
近所に相談できる育児経験者がいる間はいいですが、地域コミュニティが崩壊し、相談者もいなくなってくると、母子は孤立化し、育児不安やストレスが増し、離婚や貧困、虐待といった家庭崩壊につながってしまいます。
バブルが弾けたあとの日本は不況にあえぐことになりました。
未だ改善しない男女不平等社会は女性の就労を困難でかつ低賃金なものにし、かつて1億総中流時代という言葉が流行りましたが、今や日本の子供の7人に1人(相対的貧困率13.9% 2017)が貧困状態にあり、先進国の中でも貧困率の高い国として知られています。
また不況下では夫婦共働きが増えますから幼稚園より保育園への入所者が増えるわけですが、いつしか順番待ちしないと保育園に入れないよという「待機児童問題」が発⽣しました。
このような保育に関するサマザマな矛盾が社会問題として⼈々の知るところとなるきっかけとなったのが平成28年3⽉の匿名ブログ「保育園落ちた。⽇本死ね!」だったわけです。
日本の子育て関連の予算規模は先進国平均の半分にとどまっており、男性の家事参加率や育児参加率は世界でも最低クラスです。今日本での子育てが世界で最も難しいと言われています。
その背景には、①経済優先・高齢者優先の政治政策、②男子優先・集団の秩序優先の社会、に加えて③保育所や幼稚園の子育てに関する理解不足、職業意識の低さといったものが背景にあると考えています。。